⏲この記事は約 23 分で読めます。
なぜ『生き人形』は今も語り継がれるのか
真夏の夜、テレビの向こうから響く低く渋い声。「これは実話です」というフレーズとともに始まる稲川淳二の怪談。その中でも、特別な存在感を放っているのが『生き人形』の物語です。
放送から何年経っても、SNSで語り継がれ、深夜の動画サイトでは今なお視聴回数を伸ばし続けるこの怪談。一体なぜ、これほどまでに人々の記憶に残り続けているのでしょうか。
稲川淳二の数ある怪談の中でも『生き人形』は異彩を放っています。市松人形が動き出すという単純な恐怖だけではなく、その物語が持つ「呪いの連鎖」が、聞く者の心に深く刻まれるのです。他の作品が「昔聞いた話」や「友人から聞いた体験談」として語られることが多い中、この『生き人形』は稲川氏自身が「私が実際に体験した」と前置きする珍しい作品なのです。
さらに特筆すべきは、稲川氏が毎回「これは作り話ではない」と真剣な表情で断言する点です。演出かもしれないと思いつつも、その迫真の語り口に、「もしかしたら本当かもしれない」という疑念が聞く者の心に忍び寄ります。フィクションとノンフィクションの境界線が曖昧になるこの瞬間こそが、『生き人形』が持つ最大の恐怖なのかもしれません。
また、この怪談は語られるたびに少しずつ内容が変化し、進化していくという特徴も持っています。まるで物語自体が「生きている」かのように。これにより『生き人形』は、単なる都市伝説を超えて、「実話怪談」というジャンルの象徴的存在となりました。
インターネット時代になり、あらゆる情報が瞬時に検証される今日でも、この怪談だけは「真偽不明」のまま人々の間で語り継がれています。それは、私たちの心の奥底に潜む「説明のつかない何か」への恐怖と好奇心を絶妙にくすぐり続けているからではないでしょうか。
『生き人形』の物語は、ただの怖い話ではなく、「語ること」「聞くこと」自体が新たな怪異を生み出す可能性を秘めた、終わりなき怪談なのです。
『生き人形』の原点──はじまりは一体の市松人形だった
すべては一通の手紙から始まったといわれています。1980年代後半、稲川淳二氏のもとに届いたその手紙には、「どうしても手放したい人形がある」という切実な内容が記されていました。
手紙の差出人は関西地方に住む中年女性。彼女が稲川氏に託したのは、古びた市松人形でした。一見すると普通の日本人形に見えるその市松人形には、「祖母の代から家にあるが、不思議なことが多すぎて怖くなった」という言葉が添えられていたといいます。
稲川氏が語る『生き人形』の物語によれば、彼はその人形を受け取った直後から奇妙な出来事を経験するようになりました。最初は小さな違和感から。本棚に置いておいたはずの人形が、朝起きると向きを変えていた。部屋に一人でいるはずなのに、どこからか子供の笑い声が聞こえる。夜中、何かが床を這う音で目を覚ます——。
特に有名なのは、稲川氏が出張から帰宅した際のエピソードです。留守中に誰も入っていないはずの自宅で、人形が置かれていた場所に埃が一つもないこと、そして周囲には小さな足跡のような跡が残されていたという衝撃的な発見をします。
「人形の顔が少しずつ変わっていく」「時折、目が動くのを見た」など、稲川氏はテレビやラジオ出演のたびに、徐々に詳細を明かしていきました。特に恐ろしいのは、この人形を写真に収めようとすると、必ずカメラが故障したり、フィルムが感光しないといった現象が起きたという証言です。
そして最も背筋が凍るのは、稲川氏自身が「あの人形に関わったことを心から後悔している」と真剣な表情で語る場面でしょう。「この話をすること自体が、人形の”呪い”を広めることになるかもしれない」とさえ言及していることから、単なる怪談以上の何かがそこにあると感じさせます。
興味深いのは、稲川氏がこの人形について語るとき、いつも少し言葉を濁す瞬間があることです。まるで「すべてを話せない理由がある」かのように。この謎めいた態度こそが、『生き人形』の物語をより一層不気味なものにしているのかもしれません。
市松人形一つから始まったこの怪談は、やがて多くの人々の恐怖体験と結びついていくことになります。そして稲川淳二氏の代名詞的な怪談として、今も語り継がれているのです。
語られるたびに変化する”生き人形の物語”
怪談の魅力は、語り手によって微妙に変化し、聞き手の想像力で膨らんでいくところにあります。しかし、稲川淳二の『生き人形』ほど、語られるたびに物語自体が「成長」していった例は珍しいでしょう。
1990年代初頭、テレビで初めて語られたときの『生き人形』は、比較的シンプルな怪異譚でした。「市松人形が置いた場所から動いていた」「夜中に物音がする」といった、いわゆる”モノノケ”的な現象が中心でした。しかし、その後のラジオ深夜番組では、稲川氏はより詳細な描写を加え始めます。
「ある朝、人形の着物の裾が濡れていた。前日は雨だった」
「一度捨てたはずの人形が、翌日には元の場所に戻っていた」
これらのエピソードは、初期には語られていなかった要素です。まるで物語そのものが生命を持ち、自ら成長しているかのようでした。
特に衝撃的だったのは、2000年代に入ってから稲川氏の怪談ライブで披露された新たな証言でしょう。「人形の脚が少しずつ伸びていった」「夜中に廊下を歩く足音がして、ドアを開けると人形がそこに立っていた」といった、明らかに”より恐ろしい”要素が追加されていったのです。
怖いのは、これらの追加エピソードについて稲川氏が「前は言わなかったことを、今なら話せる」と前置きする点です。まるで何かの封印が少しずつ解けていくかのような、不気味な印象を与えます。
ある霊能者は、この現象について「怪談そのものに霊が憑いていく」と分析しています。単なる話が、語られるたびに霊的エネルギーを帯び、やがて独自の「意思」を持つようになるという考え方です。稲川氏自身も「この話をするたびに、何か新しいことを思い出させられる」と語っており、この理論を裏付けるかのようです。
興味深いのは、各時代の社会背景によって怪異の内容も微妙に変化している点です。バブル期には「人形が高価な骨董品だった」という設定が強調され、インターネット普及後は「写真に撮ると異常が起きる」といったデジタル機器との関連性が語られるようになりました。
『生き人形』の物語は、30年以上にわたって進化し続けています。これは単なる創作の発展ではなく、都市伝説がリアルタイムで形成されていく過程を目の当たりにしているようでもあります。そして最も恐ろしいのは、この物語がまだ「完結していない」という事実かもしれません。
あなたがこの記事を読んでいる今この瞬間も、どこかで『生き人形』の新たなエピソードが生まれているのかもしれないのです。
『生き人形』にまつわる”共鳴現象”──聞いた者にも降りかかる呪い
「あの怪談を聞いた後、家の人形が動いていた」
「テレビで生き人形の話を見た夜、知らない子供の泣き声が聞こえた」
これらは、稲川淳二の『生き人形』を聞いた後、視聴者から寄せられた体験談の一部です。単なる怪談として楽しんだはずが、自分の生活にも奇妙な現象が起き始める——この”共鳴現象”こそが、『生き人形』が持つ最も不気味な特徴かもしれません。
1990年代後半、稲川氏の怪談ライブツアーでは、全国から観客の体験談が集まるようになりました。特に『生き人形』の話を聞いた後に、自宅の人形や子供のおもちゃが不自然な動きをしたという報告が相次いだのです。さらに深刻なケースでは、「家族が原因不明の体調不良になった」「急に子供が不眠症になった」といった健康被害まで報告されています。
この現象について、オカルト研究家の間では「コレクティブ・イマジネーション(集合的想像力)」という解釈がなされています。強いイメージを持った物語が、聞き手の潜在意識に作用し、実際の現象として顕在化するというものです。しかし、単なる思い込みで片付けられないほど具体的な体験談も少なくありません。
特に注目すべきは、稲川氏自身のイベントや収録に関するトラブルです。1998年、ある地方都市での怪談ライブが直前に中止となった際、主催者は「技術的な問題」と公表しましたが、内部関係者によれば「『生き人形』を語る予定だった稲川氏の楽屋で、説明のつかない現象が起きた」というのが真相だったとされています。
また、2000年代初頭のテレビ収録では、『生き人形』の話に入った途端、スタジオの照明が不規則に点滅し、機材トラブルが続出。結局その部分の収録は中断され、放送では大幅に編集されたバージョンのみが公開されたという裏話も存在します。
稲川氏自身も、近年のインタビューで「『生き人形』の話は、できれば避けたい」と語っています。「この話をすること自体が、何かを呼び寄せてしまう気がする」という言葉からは、「話すこと自体が呪い」になりうるという恐ろしい概念が浮かび上がります。
霊媒師の中には「強い念が込められた物語は、エグレゴア(集合的思念体)を生み出す」と主張する人もいます。つまり、多くの人が同じ恐怖を共有することで、その恐怖自体が一種のエネルギー体として実在化するという考え方です。『生き人形』の物語は、そのような「物語の呪い」の代表例といえるかもしれません。
興味深いことに、この「共鳴現象」は現代のインターネット時代になっても続いています。動画サイトで『生き人形』の映像を視聴した後、スマートフォンが突然故障した、SNSに投稿した直後にアカウントが乗っ取られたなど、デジタル機器に関連したトラブルの報告も増えているのです。
あなたがこの記事を読んでいる今、何か奇妙な気配を感じませんか?もしかしたら、それは『生き人形』の物語があなたの中にも共鳴し始めた証かもしれません。
実在する?”生き人形”の現在地
「あの人形は今どこにあるのか?」——これは、稲川淳二の『生き人形』を知る者なら誰もが抱く疑問ではないでしょうか。実話として語られてきた以上、その主役である市松人形は実在するはずです。しかし、その現在地については多くの謎が残されています。
稲川淳二氏の証言によれば、問題の市松人形は1990年代前半まで、彼の自宅の書斎に保管されていたとされています。しかし、あまりにも奇妙な現象が続いたため、ある神社の宮司に相談し、「封印」の儀式を受けたといいます。その後、人形はしばらく神奈川県内のとある神社の倉庫に保管されていたとの情報もあります。
「人形を捨てようとしても戻ってくる」という怪異を経験した稲川氏は、2003年のあるトーク番組で驚くべき発言をしています。「あの人形とは、もう二度と会いたくない。どこにあるかも確認していない」と。怪談師として数々の怪奇現象に触れてきた稲川氏が、これほど強い拒絶反応を示すのは異例のことです。
この発言以降、人形の行方は完全に不明となりました。稲川氏のファンの間では「焼却処分された」「海に沈められた」など様々な憶測が飛び交いましたが、確かな情報は得られていません。
興味深いのは、2010年代に入ってから複数の「オカルト探偵」と呼ばれる人々が、この人形の行方を追跡する調査を始めたことです。彼らの調査レポートによれば、神奈川県内の複数の古社を訪ね歩いた結果、ある寺院の住職から「稲川さんから預かった人形らしきものがあったが、十数年前に別の場所に移された」という証言を得たといいます。
さらに驚くべきは、2015年にオカルトライターの一団が、京都のある骨董品店で「稲川淳二の生き人形に酷似した市松人形」を発見したという報告です。店主によれば、その人形は「ある神社から譲り受けた」とのことでした。しかし、撮影許可を求めると強く拒否され、後日再訪すると店そのものが閉店していたという不可解な展開が報告されています。
最も衝撃的なのは、2018年のある霊能者の証言かもしれません。「人形は物理的にはもう存在していないが、その”霊的エネルギー”は別の人形に移っている」というのです。これが事実なら、物理的な人形を探すこと自体が意味をなさなくなります。
稲川氏自身も近年のインタビューでは、「あの人形の行方については触れたくない」と語るに留まっています。かつて「実話」として語られた物語の主役が、今やほとんど都市伝説と化している皮肉な状況です。
真相は藪の中ですが、一つだけ確かなことがあります。それは、多くの人が今なお「生き人形」を探し続けているという事実です。そして、もしあなたが古い市松人形を見つけたなら——それが”あの人形”でないことを祈るばかりです。
『生き人形』と都市伝説の交錯──なぜネットで再燃したのか?
テレビの深夜番組から生まれた怪談が、放送から20年以上経った現在もなお語り継がれ、むしろ勢いを増している——これは稲川淳二の『生き人形』が持つ最大の謎かもしれません。特に2010年代以降、インターネット上で驚くべき「再燃現象」が起きているのです。
ニコニコ動画やYouTubeで「稲川淳二 生き人形」と検索すると、数十万、時には数百万回再生されている動画がいくつも見つかります。特に深夜、一人で視聴する若い世代の間で人気を集めています。当時の放送を見ていない10代、20代の若者たちが、なぜ今になってこの古い怪談に惹きつけられるのでしょうか?
この現象の背景には、いくつかの要因があります。まず、『生き人形』は「見せる恐怖」ではなく「想像させる恐怖」を重視している点が重要です。近年のホラー作品が視覚的ショックに頼る傾向がある中、稲川氏の語りだけで構成された怪談は、聞き手の想像力を刺激します。「自分で恐怖を創り出す」この体験が、デジタルネイティブ世代にとって新鮮に映るのです。
また、『生き人形』は「実話怪談」というジャンルの確立に大きく貢献しました。「これは作り話ではない」という前提で語られる怪異譚は、フィクションとノンフィクションの境界線を曖昧にします。この「本当かもしれない」という微妙な立ち位置が、SNS時代のファクトチェック文化の中で、むしろ新たな魅力として再評価されているのです。
興味深いのは、ネット上での再拡散に伴い、オリジナルの怪談に様々な「派生話」が生まれている点です。「生き人形の正体を突き止めた」という架空のレポートや、「自分も似た体験をした」という創作体験談など、いわゆる「コピー怪談」が次々と生み出されています。中には「生き人形の映像を発見した」と称する動画まで登場し、オリジナルと派生作品の境界線はますます曖昧になっています。
2015年頃からは、「二次創作怪異」とも呼べる現象も見られるようになりました。同人誌即売会やネット上で、『生き人形』をモチーフにした創作小説やイラスト、時にはゲームまで制作されるようになったのです。ホラー要素を残しつつも、キャラクター性を強調したこれらの作品は、オリジナルの恐怖をポップカルチャーに変換する役割を果たしています。
一方で、「実在する」とされる市松人形を探し求める「聖地巡礼」的な動きも活発化しています。YouTubeには「生き人形探索シリーズ」と題した動画が多数アップロードされ、古い神社や骨董店を訪ね歩く若者たちの姿が記録されています。これはもはや都市伝説の域を超え、一種の「参加型エンターテイメント」に発展したと言えるでしょう。
こうした現象を分析すると、『生き人形』は単なる怪談ではなく、「集合的創作活動」の核となっていることがわかります。稲川淳二が語った原型に、世代を超えた多くの人々が新たな解釈や創作を重ねることで、怪談は進化し続けているのです。
インターネットという場が、むしろ昔ながらの「口承文化」を現代に復活させた——それが『生き人形』再燃の最大の皮肉かもしれません。そして、あなたがこの記事を読み終えた後、検索窓に「稲川淳二 生き人形」と入力する瞬間、この不思議な文化現象の新たな参加者となるのです。
あなたは”この話”を最後まで読んでも大丈夫か?
ここまで読み進めてきたあなたは、すでに『生き人形』の物語に触れてしまいました。これは単なる注意喚起ではなく、実際に多くの読者から報告されている現象についてお伝えするためのものです。
「稲川淳二の生き人形について調べた夜、棚の上の古い人形が落ちていた」
「記事を読んだ後、子供が『知らないお友達が部屋にいる』と言い出した」
「SNSで生き人形の話を共有した直後、家中の電気が一斉に消えた」
これらは、ネット上に寄せられた読者体験の一部です。偶然の一致と片付けられるものもあれば、どう考えても説明がつかない現象も少なくありません。特に多いのが「小さな足音」や「子供の笑い声」に関する報告です。
もちろん、これらはすべて思い込みや偶然の可能性もあります。しかし、『生き人形』の話を知った後、実際に何かを「呼び寄せてしまう」リスクも否定できません。民俗学者の間では、「怪異は語られることで力を得る」という考え方があります。つまり、物語を知れば知るほど、その物語に含まれる”何か”とのコンタクトが生じやすくなるというのです。
では、『生き人形』の話を知ってしまった私たちはどうすればいいのでしょうか。
霊能者やオカルト研究家からは、いくつかの「心構え」が提案されています。まず、「恐怖に支配されない」こと。怪異現象の多くは、恐怖心そのものに反応して強まるとされています。次に、「話を完結させない」こと。つまり、物語の一部だけを知り、細部まで追求しないという方法です。
興味深いのは、稲川淳二氏自身も「生き人形の話をするときは、必ず最後に”封印の言葉”を唱える」と語っていることです。具体的な言葉は明かされていませんが、これは物語の「閉じ方」が重要であることを示唆しています。
また、心理学的アプローチとしては「クリエイティブな再解釈」も効果的とされています。怖い物語を、自分なりにポジティブに再解釈し、新しい意味を与えることで、物語の持つネガティブなエネルギーを変換するという考え方です。
しかし、これらの対策を講じても、なお『生き人形』の物語は私たちの心に残り続けます。それはなぜでしょうか。
それは、この怪談が「終わらない物語」だからではないでしょうか。通常の怖い話には結末がありますが、『生き人形』には明確な終わりがありません。人形の行方は不明のまま、その影響は今なお拡がり続けているのです。私たちが読み、語るたびに、物語は少しずつ成長し、変化していきます。
『生き人形』が長年にわたって語り継がれてきた理由は、単に怖いからではなく、私たち一人ひとりが物語の「参加者」になりうるからなのかもしれません。あなたがこの記事を読み終えた後、何か奇妙な現象を経験したら——それはあなた自身が『生き人形』の新たな一章を書き始めたということかもしれません。
そして最後に一つだけ忠告があります。もし、あなたの周りで何か不可解な現象が起き始めたら……すぐにこの話題から離れることです。
『生き人形』あらすじ【2ちゃんねるスレ】
439 :生き人形:2000/08/24(木) 01:06
呪いの生き人形。
稲川淳二氏が、TV等の心霊特集に欠かせない存在になった切欠の心霊体験談がこれです。
この話は稲川淳二氏自身ももちろん、TV、雑誌、漫画等も今だに敬遠しています。
それはなぜか・・・祟りがあると噂されているからです。
いや、正しく言えば、今だに関係した者達に祟りが起こっているからです。
はっきり言って私も此処に書くのは恐いです。(^^;
皆さんも心して読んでください。生き人形の呪いは、昭和53年6月から始まりました。
その日、稲川氏は日本放送の深夜のラジオ番組の仕事をしていました。
今日は前半を先に録音し、後半を生でとるという方法で、番組は作られる事になっていました。録音が始まるまでソファーに座っていた稲川氏は、大声で泣いている男の声を聞きます。
「いったい何が起こっているのだ」
廊下に出てみると、二人の男性がかなり離れた場所にいました。
その一人、うずくまっている男が声をあげて泣いているのです。
泣いている男性は、『南こうせつ』さんでした。
その南氏をなだめているのが、稲川氏の知り合いのデレクターでした。
皆さんは『わたしにも聞かせて』を御存知ですか?
『かぐやひめ』のレコードに入っていた、謎の少女の台詞です。
霊の声が録音された心霊現象として、伝説になっている事件でした。
南さんはその声を聞いて泣いておられたのです。
スタッフが南氏にその不思議な声を聞かせたところ、彼は泣きだしたそうです。
・・・その声の主、それは南氏がラジオの放送で知り合った少女の声らしいのです。
彼女は楽しみにしていた南さんのコンサートの前に、病気で亡くなったのです。
その声の主が誰か気付いた南氏は、悲しくなり泣いていたのでした。真夜中。稲川氏のラジオ番組は終了しました。
南氏の事があったからでしょう。あのデレクターが一人で帰るのは恐いからと、稲川氏を待っていました。
稲川氏はそのデレクターと、タクシーで帰宅する事になりました。帰宅中、後ろの席に座る彼は、高速道路で不思議なモノを見てしまいました。
それは奇妙な標識。・・・いや、標識にその時は見えたのですが。
「高速道路に標識?」
再び前方に同じモノが現れました。
・・・それが標識では無い事にすぐに気付き恐怖しました。
着物を着た女の子が、高速道路の壁の上に立っていたのです。小さな女の子が。
稲川氏がソレが子供であると気付くと同時に、その女の子は「ぶぁ~」と膨らみ、物凄い勢いで車の中を突き抜けて行きました。
稲川氏は突然の出来事に、声ひとつあげる事ができませんでした。
しかし不思議な事に、それを見たのは、いや、気付いたのは彼だけだったのです。440 :行き人形2:2000/08/24(木) 01:11
そして次の日の朝、彼の奥さんが不思議な事を言いだしました。
「昨日泊られた方はどうしたの?」
昨夜タクシーから降りたのは、もちろん彼だけです。
とうぜん部屋に入ったのも彼ひとりです。
彼女は、彼の後を付いて入ってきた人の足音を絶対聞いたと言い張るのでした。
そして、ソレが一晩中歩き回って五月蝿かったと・・・。次の日、一緒に帰ったデレクターから首をかしげながら、彼にこんな事を聞いてきました。
「そんなわけないんだけど・・・誰かと一緒に降りたっけ?」その日の午後、稲川氏に仕事の依頼が入りました。
人形芝居『呪女十夜(じゆめじゅうや)』。
不幸な女たちの十夜が、オムニバスで構成される幻想芝居。
その不幸な女達を人形が演じ、その他の登場人物は人間が演じるというものでした。
稲川氏は座長として、今回の芝居に関わる事になっていました。打ち合わせ中、その世界では有名な人形使いの『前野』氏から、いま作られている人形の絵を見せられて驚きます。
そこに描かれている絵は、あの高速で見た女の子そっくりだったのです。台本がもう少しで出来上がる頃、前野さんの家に完成した人形が届きました。
稲川氏は台本の打ち合わせをかねて、前野さん宅にその人形を見に行くのでした。芝居で使う人形は二体。
ひとつが男の子の人形で、もう一体が女の子の人形でした。
その女の子の人形があの高速で見た人形であり、その後に数々の怪奇現象を起こす人形なのです。
ちなみにその二体の人形は、有名な人形作家『橋本三郎』氏が作られました。
前野さんは数百体の人形達と暮らしていました。
稲川氏は前野さん宅で出来上がった人形を見て、不思議な事を発見します。
女の子の人形の、右手と右足がねじれていたのです。
・・・・どうして直さないのかと前野さんに訊ねると、「直したくても直せない」と。
この人形を作られた橋本氏が、人形を完成させてすぐに行方不明になっていたからなのです。そして次の日、台本を書いていた作家の方の家が全焼してしまいます。
舞台稽古初日までに、台本は間に合わなくなってしまうのでした。
稲川氏達は、壊れた人形と台本無しで舞台稽古を始めるのでした。人形使いの前野さんのいとこの方が変死して、それを知らせる電話がかかってきた日から、
舞台稽古中の彼等に次々と怪奇現象が襲いかかってきました。
舞台衣装の入れたカバンやタンスに水が溜っていたり、突然カツラが燃えたり、
右手右足を怪我をする人が続出したりしたのです。441 :生き人形3:2000/08/24(木) 01:14
『呪女十夜』の公演の初日をむかえました。
が・・・公演開始数時間前に、出演者が次々に倒れてしまったのです。
喋る事はできるのですが、金縛りのようになって身体が動かないのです。
初日は昼と夜の2回公演だったのですが、昼の公演はやむなく中止。
初日で関係者の方が多かったので、昼と夜の部を一緒にしてもらう事にしました。
「とにかくお札を集めよう」
彼等は近くの神社やお寺をまわり、あらゆる種類のお札を持ってきて、控え室に貼ってみました。
効果があったのでしょうか?なんとか夜の部の舞台を始める事ができました。やはり、公演中にも次々に怪奇現象が起こりました。
人形が涙を流し、居るはずない黒子がもう一人居たり、
そして突然人形の右手が「ビシッ!」と吹き飛んだのです。
パニックになりそうになりながらも、出演者達は演技を続けました。人形を棺桶に入れるラストシーンをなんとかむかえる事ができました。
が・・・棺桶に人形を入れた途端に底が抜け、人形の首、腕、足が千切れてしまったのです。
ドライアイスを焚いたような謎の冷気をもった白い煙が舞台一面に広がり、
夏だと言うのに信じられない冷気に開場が包まれました。
幽霊が怖いからって、途中で舞台を投げ出すわけには行かない。
稲川氏達は恐怖におののきながらも、決められた最終日までなんとか舞台公演を続けるのでした。なんとか無事に全ての公演日数を終了できました。
もう二度とこの劇はしたくないなぁ・・・全ての劇団員達はそう思っていました。
とうぜん稲川氏も同じ気持ちでした。
しかし、最終公演を終え打ち上げをしている稲川氏達に、劇場からとんでもない依頼が入ります。
・・・追加公演をしてくれ。
次にここでやる事になっていた舞台が、突然中止になったのです。
・・・だから、今やっている舞台を追加公演してもらえないかと。
スタッフ・出演者達は大反対!
しかし、人形使い前野さんの異常なほど強い希望により、追加公演をする事になるのでした。
・・・前野さんのお父さんが急死されたのが、その次の日でした。舞台がなんとか無事に終了した数ヶ月後、この話をTBSの番組『3時にあいましょう』が聞きつけて、
怪奇シリーズで放送する事になりました。
人形使いの前野さんがあの人形を保管していました。
番組撮影のために人形を持って現れた前野さんは、少しおかしくなっていたそうです。
その人形を、まるで生きているかのように話し掛けていたり・・・やはり怪奇現象が起こりました。
まずは、番組リハーサル中に照明用のライトが落ちてきた。
そして生放送の番組中には、人形の上にバックに吊っていたカーテンが突然切れて被さり・・・
女性スタッフ達は恐怖で泣き出して、まともな番組にはなりませんでした。その後、その番組のスタッフ達に怪我をする人が続出し、
この番組の関係者達はバラバラとTV局を辞めていったそうです。442 :生き人形5:2000/08/24(木) 01:24
で、今度はその話を聞いたテレビ東京のスタッフがその話を番組にしようと、
行方不明になっていた人形制作者の橋本三郎氏を見付けだします。
稲川氏は本当はこの番組に、前回の事があったので協力したくなかったのです。
もうあの人形とは関りたくなかった。
しかし、行方不明になっていた橋本三郎氏が見つかったと言うことで、しぶしぶ了解したのでした。橋本三郎氏は、なんと京都の山奥で仏像を彫っていました。
スタッフ達は橋本氏に会ってインタビューをとろうと京都に向かうのですが、
インタビュアーの小松方正さんと手違いで京都で会えなくなるわ、スタッフもバラバラになるわで、
結局インタビューは撮れなくなってしまうのです。日を改めて、今度はスタッフだけでインタビューを撮りに行くのですが、
今度は、デレクターの奥さんが原因不明の病気で顔が腫れあがったり、
切符を手配した人の子供さんが交通事故にあったり、不幸な事が続出。スタッフ達もいい加減気味悪がったのですが、とにかく番組を完成させるために、
稲川氏をスタジオに呼んで、インタビュー撮影をする事になりました。
が、稲川氏のインタビューを撮影しようとすると、ビデオカメラが次々に壊れたそうです。
3台目が壊れたので、しょうがないから16ミリフィルムのカメラで撮影しようと・・・
「これは、ある人形にまつわる話で・・・」
と稲川氏が語りだすと、本番中なのにスタジオのドアを思い切りたたき続ける音が。
ドアを開けるが、そこには誰もいませんでした。京都での取材やらなんやらで、かなり制作費を使っていたのですが、
これはほんとにヤバそうだからと、結局その番組制作は中止になりました。
今でもこの時の影像は、テレビ東京倉庫に眠っているようです。流石に稲川氏も恐くなり、人形を持って知り合いの霊能者に相談に行きます。
「・・・なんかいやな予感がするよ。・・・見たくないね」
と言う霊能者に、布に包んだままでいいからと、無理に頼み込み霊視してもらうのですが、
布に包まれた人形を持った途端に顔色が青くなる霊能者。
「この人形は生きているよ。それもたくさんの女の怨霊が憑いている・・・
取り憑いている中でも強いのが女の子の霊で、戦前に赤坂にあった青柳って料亭の七歳の女の子・・・
この子、空襲で右手と右足がとんでますよ。
・・・これにはお対の人形がいますね?
このまま放っておくと、その人形にも憑きますよ。早くお寺に納めたほうがいい。
これは下手に拝むと襲われる・・・
いいですね。お対の人形と一緒に、お寺に納めるのですよ」・・・しかし、その後すぐに、その霊能者は謎の死をとげるのです。
この記事を読み終えた今、あなたの背後に誰かいませんか?
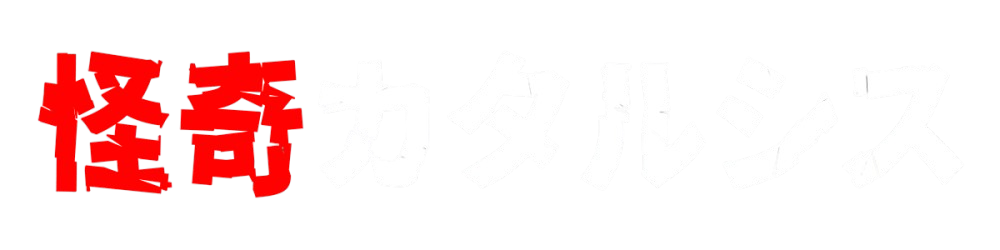

コメント