⏲この記事は約 17 分で読めます。
噴火は“遠い出来事”ではない
「火山の噴火」と聞いて、あなたはどんなイメージを思い浮かべるでしょうか? もしかすると、「どこか遠い山の話」「めったに起きないこと」と感じているかもしれません。しかし実際には、日本に住んでいる限り、噴火は決して“他人事”ではありません。
日本は、世界でも有数の火山大国です。気象庁によれば、現在も活動を続ける「活火山」は111座。これは世界の活火山の約1割にあたります。そして、それらの多くが人口密集地の近くに存在しているのが、日本の大きな特徴です。
記憶に新しいのは、2014年の御嶽山(長野・岐阜県)の突然の噴火。紅葉シーズンに登山者が多く訪れる中、前兆の少ない水蒸気噴火が発生し、58人もの尊い命が奪われました。2011年以降も桜島(鹿児島)では噴火が頻発し、日常的に降灰被害が出ています。
さらに、南海トラフ地震や首都直下型地震と並んで、火山噴火も“いつ起きてもおかしくない”自然災害として、国や自治体が対策を進めています。
では、今もしも――
富士山が噴火したら?
箱根山が爆発的な活動を始めたら?
阿蘇山が再び巨大噴火を起こしたら?
その影響は、単に山の近くに住む人々だけでなく、首都圏や日本全体の経済・生活インフラにも及びます。
この記事では、もし噴火すれば甚大な被害が出ると考えられている「日本の危険な火山10選」を紹介しながら、火山災害への備えやリスク認識を一緒に考えていきます。
「火山は今も生きている」――
その現実を、まずは知ることから始めましょう。
日本にある火山の数と危険度の現実
日本は、世界でも指折りの「火山大国」であることをご存じでしょうか?
その理由は、地球のプレートがぶつかり合う「火山帯」の真上に日本列島が位置しているからです。
実際に、日本には約110の活火山が存在します(2024年時点で気象庁が指定しているのは111座)。これは世界全体の活火山の約1割にあたり、国土の面積に対する密度としては世界でもトップクラスです。
「活火山」とは何か?
まず、そもそも「活火山」とはどんな火山を指すのか。
気象庁の定義では、概ね過去1万年以内に噴火したことがあり、現在も噴気活動などが観測されている火山を「活火山」と呼びます。
つまり、「何百年も噴火していないから安全」というわけではなく、静かに“生きている”火山が日本中に点在しているということです。
火山の警戒レベルってどうなってるの?
さらに、火山の活動状況を示す指標として使われているのが、「噴火警戒レベル」です。これは気象庁と火山噴火予知連絡会が中心となって運用しているもので、現在はレベル1~5の5段階で構成されています。
| レベル | 説明 | 対応行動の目安 |
|---|---|---|
| レベル1 | 活火山であることに留意 | 通常の登山・観光は可能 |
| レベル2 | 火口周辺規制 | 火口周辺への立ち入り禁止 |
| レベル3 | 入山規制 | 山全体への立ち入りを制限 |
| レベル4 | 避難準備 | 周辺住民は避難の準備を開始 |
| レベル5 | 避難 | 居住地域からの避難が必要 |
この警戒レベルは、火山の観測データ(地震活動、地殻変動、噴煙の高さなど)に基づいて、随時見直されます。
たとえば、2023年には十勝岳や浅間山がレベル2に引き上げられ、一部エリアが立ち入り禁止になりました。また、桜島や諏訪之瀬島のように、日常的に噴火が起きている火山もあります。
火山は「見た目の静けさ」にだまされてはいけない
多くの人が「見た目が穏やかだから安全」と思いがちですが、火山は活動の兆候を表に出さないことも多いのです。
過去の噴火でも、前兆がほとんどないまま突然爆発的な活動に移行した例があります。
つまり、「あの山は静かだから大丈夫」と思っている時こそ、最も注意が必要なのかもしれません。
噴火したら甚大な被害が出る可能性のある火山10選
ここでは、日本にある活火山の中でも「噴火した場合、都市機能や広域社会に深刻な影響を及ぼす」とされている代表的な火山を10座、取り上げます。
1. 富士山(山梨・静岡)

Mocchy – 原版の投稿者自身による著作物 (Original text: 本人撮影。), パブリック・ドメイン, リンクによる
→ 首都圏に降灰、交通麻痺、物流停止の危機
日本人なら誰もが知る「富士山」。その美しい姿は世界遺産としても評価され、観光地としてのイメージが強いですが、実は常に“次の噴火”が警戒されている活火山でもあります。
◆ 宝永噴火の記憶は300年前。次はいつ?
富士山が最後に大規模な噴火を起こしたのは1707年の「宝永噴火」。当時は江戸(現在の東京)にも火山灰が積もり、農作物の壊滅や飢饉につながる深刻な被害を出しました。
あれから300年以上、富士山は静かに見えますが、火山活動は地下で静かに進行している可能性があります。
実際、近年は山体周辺で火山性地震や地殻変動が観測されており、「前兆なしで噴火するリスクも否定できない」と専門家は指摘しています。
◆ 噴火したらどうなる?──現代社会へのインパクト
現代の富士山噴火は、単なる自然災害にとどまりません。
被害は首都圏のインフラと経済活動に直接的な打撃を与えます。
-
大量の火山灰が東京を覆い、高速道路や鉄道、空港が麻痺
-
変電所や太陽光パネルに灰が積もり、停電や電力供給停止の恐れ
-
物流の停止により、スーパーの棚から商品が消える可能性も
-
降灰による呼吸器への健康被害、学校・企業の閉鎖
内閣府の試算では、富士山噴火による直接的な経済損失は最大で2兆5,000億円以上とされており、これは東日本大震災に匹敵する規模とも言われています。
◆ 富士山は“今も生きている”
現在、富士山の噴火警戒レベルは「レベル1(活火山であることに留意)」ですが、それは「安全」という意味ではありません。火山性地震の観測や、2011年の東日本大震災以降に地下の圧力が変化したとする調査報告もあり、噴火の可能性はゼロではありません。
私たちが知っている富士山の“静けさ”は、もしかすると嵐の前の静けさかもしれないのです。
美しさの裏に潜む、もうひとつの富士山の顔。
それを正しく理解することが、未来の災害を防ぐ第一歩になるのかもしれません。
2. 桜島(鹿児島)

TANAKA Juuyoh (talk) – https://www.flickr.com/photos/13910409@N05/3290954157, CC 表示 3.0, リンクによる
→ 日常的な噴煙も、爆発的噴火のリスクは依然大
鹿児島県の象徴とも言える桜島。ほぼ毎日のように噴煙を上げるこの火山は、「活火山」というよりも「常に活動している火山」と言ったほうがふさわしい存在です。
市街地からわずか数キロに位置し、**“人が暮らす街の隣で火山が生きている”**という世界でも極めて珍しい地域。
鹿児島市民にとっては見慣れた光景かもしれませんが、その“慣れ”こそが、もっとも危険なのかもしれません。
◆ 「見慣れた噴煙」の裏にある危機
桜島では、日常的な小規模噴火が続いています。2024年も噴火回数は年間500回以上。
しかし、こうした継続的な活動の背後には、巨大噴火(大規模マグマ噴火)へのステップという見方もあります。
実際、1914年の「大正大噴火」では、島が本土と地続きになるほどの溶岩流が発生し、死者・行方不明者は数十人にのぼりました。
さらに桜島は、「今後30年以内に大規模噴火が起きる可能性が約1%」とする予測もあり、これは「南海トラフ地震と同等レベルのリスク」と言われています。
◆ 都市への被害が“リアルに想定されている”火山
もしも桜島で爆発的な噴火が起きた場合、以下のような深刻な被害が想定されています:
-
火砕流が鹿児島市街地に到達する可能性
-
10万人以上が短時間で避難を迫られる
-
空港・港湾・病院などの都市インフラが機能不全に
-
火山灰による健康被害や水道汚染
火砕流や溶岩流に対して避難できる時間はわずか数十分とされており、「初動対応が生死を分ける」火山災害の最前線にあるのが桜島です。
◆ 現在の状況と監視体制
2025年現在、桜島の警戒レベルは「レベル3(入山規制)」。
火口から半径2km以内は立入禁止区域となっており、火山性地震や噴気の状況は常に気象庁が監視しています。
また、地元自治体も避難ルートや防災無線の整備を進めており、「いつ噴火してもおかしくない」という前提で暮らす人々の覚悟がうかがえます。
“噴火と共に生きる”という現実。
桜島が教えてくれるのは、火山との共存には準備と知識、そして覚悟が必要だということかもしれません。
3. 阿蘇山(熊本)

日本語版ウィキペディアのSonataさん, CC 表示-継承 3.0, リンクによる
→ 巨大カルデラ噴火が起きれば九州壊滅レベル
熊本県にそびえる阿蘇山は、今なお活動を続ける活火山でありながら、観光地としての顔も持つ存在です。しかし、その穏やかな姿の奥には、“日本最大級の破局噴火を引き起こした火山”というもうひとつの顔があります。
およそ9万年前に発生した「阿蘇4」と呼ばれるカルデラ噴火では、火砕流が九州を覆い尽くし、その火山灰は北海道や朝鮮半島にまで達したといわれています。もし同規模の噴火が現代に起きれば、九州全域が壊滅的被害を受けるのは確実。まさに“想像を絶する”規模の自然災害です。
近年の活動では、2016年に爆発的噴火が発生し、高さ11,000メートル以上にまで噴煙が立ち上がる事態となりました。この時は人的被害は出なかったものの、火口周辺では火山弾の飛散や降灰による交通障害が発生しました。
阿蘇山の噴火によって起こりうる主な被害は以下の通りです:
- 火砕流が山麓の町を襲い、数万人規模の避難が必要に
- 火山灰が九州一円に降り注ぎ、交通・ライフラインが麻痺
- 農業・畜産業・水資源への壊滅的打撃
- 広域避難と経済損失による社会機能の停止
現在の警戒レベルは「レベル2(火口周辺規制)」。活動は比較的落ち着いているとはいえ、火口直下では地熱とガスの放出が常に観測されており、地下に巨大なマグマ溜まりを抱える火山としての潜在力は決して侮れません。
「観光地として親しまれている=安全」という錯覚こそが、最大のリスクかもしれません。阿蘇山は、静かに、そして確実に次の活動の“時”を待っているのです。
4. 十勝岳(北海道)

alpsdake – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる
→ 観光地美瑛に近く、泥流被害も懸念
北海道の大雪山系に連なる十勝岳。美しい山並みと雄大な自然に囲まれ、四季折々の風景を求めて多くの観光客が訪れる場所ですが、この山もれっきとした活火山です。しかも、ただの噴火ではなく「泥流災害の脅威」を伴う火山として知られています。
最も記憶に残るのは1926年の噴火。このときは大規模な火山泥流が発生し、山麓の村々を一瞬で飲み込み、死者・行方不明者144名を出す大惨事となりました。泥流は火山灰と水が混ざって時速数十kmで流れ下り、建物や橋、人々の生活を容赦なく押し流しました。
現在も、十勝岳は「活発な状態」とされ、近年も小規模な噴火や火山性地震が発生しています。気象庁による2025年の警戒レベルは「レベル1」ですが、地元では常に火山活動への警戒が怠られていません。
もし噴火が起きた場合、想定される被害は以下のとおりです:
- 美瑛・上富良野など観光地エリアへの火山泥流の流入
- 河川の氾濫、道路寸断、避難困難地域の孤立
- 農地や牧草地の広範な汚染による経済的損失
- 観光産業への打撃と風評被害
特に、春から夏にかけては雪解け水の量が多く、噴火と同時に泥流災害が発生しやすい季節でもあります。
見渡す限りの絶景の裏には、かつて村を消した濁流の記憶が今も静かに眠っています。
美しさと脅威が隣り合わせにある――十勝岳は、自然の“二面性”を如実に語る存在なのです。
5. 雲仙岳(長崎)
Chris 73 / Wikimedia Commons, CC 表示-継承 3.0, リンクによる
→ 1991年の火砕流を忘れてはいけない
長崎県・島原半島にそびえる雲仙岳。その名を聞いて、多くの人が思い出すのは1991年、平成噴火災害の象徴ともなった“火砕流”の惨劇ではないでしょうか。
当時、噴火活動を続けていた雲仙岳の一峰・普賢岳から発生した大規模な火砕流は、瞬く間にふもとの町を襲い、住宅や道路を焼き尽くしました。この災害で火山観測者や報道関係者など43名が犠牲に。火砕流の恐ろしさと、火山災害の「予測困難性」が日本中に強く刻まれることとなったのです。
雲仙岳は、実は“長い眠り”の後に活動を再開するタイプの火山です。普賢岳の噴火も約200年ぶりの出来事でしたが、突如として噴火し、人的被害を伴う火砕流を発生させるという性質は、現在も変わっていません。
今後、再び活動が活発化した場合、以下のような被害が想定されています:
- 島原市・南島原市などへの火砕流・土石流の発生
- 斜面崩壊による急激な地形変化と河川の氾濫
- 避難指示が間に合わない“即時災害”の可能性
- 観光・農業・漁業など地域産業への壊滅的影響
雲仙岳は2024年現在、噴火警戒レベル1ですが、気象庁や地元自治体は監視を強化しています。住民の多くは防災意識が非常に高く、避難訓練や情報共有の体制も整備されていますが、それでも自然の猛威の前では“万全”とは言い切れません。
あの火砕流から30年以上が経った今、記憶が薄れつつある世代にも、もう一度伝えたいことがあります。
「雲仙岳は今も生きており、再び牙をむく可能性がある」という事実を。
6. 蔵王山(宮城・山形)

→ 火口湖「お釜」が崩れれば噴火と泥流のWリスク
東北地方を代表する名峰・蔵王山。その象徴的存在が、神秘的なエメラルドグリーンの火口湖「お釜」です。観光地として人気が高く、四季を通じて多くの人々が訪れますが、この美しい火口湖の下には、活発な火山活動を続ける“生きた火山”が眠っているのです。
蔵王山は過去にも幾度か小規模な噴火を起こしており、特に「水蒸気噴火」のリスクが高い火山とされています。地下の熱と水が反応して突発的に爆発を起こすこのタイプの噴火は、前兆がつかみにくく、避難が間に合わない可能性もあります。
さらに蔵王にはもう一つの懸念があります。それが、「お釜」周辺の地形崩壊による火山泥流(ラハール)です。大量の水をたたえるお釜が地震や噴火で決壊すれば、濁流が一気に山麓へと流れ下り、周辺集落を襲う二重災害となりかねません。
予測される主な被害は以下の通りです:
- お釜の崩落による火山泥流が白石市など市街地へ流入
- 突発的噴火による登山客・観光客の被災リスク
- 観光業・温泉地の経済的打撃
- 河川の氾濫やインフラ被害による長期的影響
2025年現在、蔵王山の噴火警戒レベルは「レベル1」。大きな活動は見られていませんが、2015年には火山性地震が急増し、一時は火口周辺への立入が制限されたこともあります。
「静けさの中に潜む危機」――それが蔵王山の本質です。
美しい火口湖の絶景の裏に、私たちは“目に見えないリスク”があることを忘れてはなりません。
7. 鳥海山(秋田・山形)

kyohei ito, CC 表示-継承 2.0, リンクによる
→ 東北の田園地帯に影響、隠れた危険火山
秋田県と山形県にまたがる鳥海山は、四季折々の美しい自然が広がる東北の名峰です。しかし、その穏やかな山容とは裏腹に、実は活発な活動を続ける“隠れた危険火山”としての顔を持っています。
鳥海山の噴火は、数百年周期で起こっており、近年でも1700年代以降に複数回の噴火記録があります。山麓には広大な田園地帯が広がっており、もし大規模な噴火や火山泥流が発生すれば、農業をはじめ地域の生活基盤に甚大な影響を及ぼす可能性があります。
過去の噴火では溶岩流や火山灰が広範囲に拡散し、山麓の集落は壊滅的な被害を受けました。現在も鳥海山は火山性地震や噴気活動が観測されており、今後の活動再開に備えた警戒が必要です。
主な懸念事項は以下の通りです:
- 田園地帯への火山灰降下による農作物被害
- 山麓集落への火山泥流や土砂災害のリスク
- 交通網やライフラインの寸断
- 地域経済への長期的なダメージ
2024年現在、鳥海山の警戒レベルは「レベル1」で、火山活動は比較的穏やかですが、山の活動性を示す微小な地震は頻発しています。
東北の豊かな自然と暮らしを守るためにも、鳥海山の動向に目を離せません。静かな山の裏側に潜む危険を、今こそ知っておく必要があるのです。
8. 浅間山(群馬・長野)

日本語版ウィキペディアのBehBehさん, CC 表示-継承 3.0, リンクによる
→ 首都圏にも灰が届く可能性
群馬県と長野県の県境に位置する浅間山は、活発な噴火活動で知られる日本有数の活火山です。江戸時代から現在に至るまで繰り返し噴火を起こしており、そのたびに広範囲に火山灰を降らせてきました。
特に浅間山の噴火は、首都圏を含む関東地方にも火山灰が降る可能性が高いことが特徴。もし大規模噴火が発生すれば、東京や横浜、埼玉といった都市部の交通網や物流、日常生活に大きな混乱がもたらされる恐れがあります。
過去の噴火では、火山灰が厚く積もり農作物被害や呼吸器系への健康被害も報告されており、火山灰がもたらす影響は決して局地的なものにとどまりません。さらに、浅間山は活火山の中でも火砕流や溶岩流の発生もあり、周辺の住民にとって常に注意が必要な存在です。
現在の浅間山は、気象庁による火山活動の監視体制が厳重に敷かれており、2025年時点での警戒レベルは「レベル2」。火口周辺への立ち入り制限が実施されています。
浅間山の噴火がもたらす主なリスクは以下の通りです:
- 首都圏まで届く火山灰による交通障害や物流の停滞
- 周辺地域での火砕流や溶岩流による直接被害
- 健康被害や農業・観光業への長期的な影響
- 緊急避難を余儀なくされる住民の増加
東京からわずか約150キロの距離にある浅間山。遠い存在ではなく、私たちの生活に直結する“身近な危機”として、常に注視が必要な火山なのです。
9. 羊蹄山(北海道)

Oga, CC 表示-継承 3.0, リンクによる
→ 「蝦夷富士」の異名、長年静かでも油断は禁物
北海道の名峰、羊蹄山はその美しい円錐形の山容から「蝦夷富士」とも呼ばれ、多くの登山者や観光客に親しまれています。しかし、その静かな佇まいの裏には、いつ活動を再開してもおかしくない活火山のリスクが潜んでいることを忘れてはなりません。
羊蹄山の最後の大噴火は約3,000年前とされ、その後は比較的穏やかな状態が続いていますが、近年も火山性微動や地震が観測されており、完全な沈静化とは言えない状況です。静けさに隠れた危険は、「眠れる巨人」のごとく、突然の噴火で周辺地域に甚大な被害をもたらす可能性があります。
噴火が起きた場合の影響は以下の通りです:
- 倶知安町や京極町などの周辺市街地への火山灰降下と火砕流の危険
- 農業や観光業への深刻なダメージ
- 河川の氾濫や土砂災害による広範囲の被害
- 避難人口の増加による社会的混乱
北海道の冬の厳しい環境も相まって、噴火時の避難や復旧活動は一層困難になる恐れがあります。警戒レベルは現在「レベル1」ですが、地元自治体と気象庁は継続的な監視と情報発信に努めています。
雄大な自然美の陰に潜む羊蹄山の脅威。
「蝦夷富士」の名にふさわしいその威容は、私たちに自然の驚異と共存の大切さを静かに教えているのです。
10. 箱根山(神奈川)

Sonata, CC 表示-継承 3.0, リンクによる
→ 首都圏観光地・温泉街が一瞬で孤立するリスク
首都圏からのアクセスも良く、多くの観光客で賑わう箱根山。しかし、その人気の裏には大きな危険が潜んでいます。箱根山は活火山群の一つであり、複数の火口が点在。過去にも度々噴火を繰り返し、その火山活動は決して収まっていません。
もし大規模な噴火が起きれば、火山灰や火砕流が箱根の温泉街や観光地を直撃し、交通網が寸断されることで瞬時に孤立状態に陥るリスクがあります。国道や鉄道、登山道路が閉鎖され、避難や救援活動が極めて困難になる恐れがあるのです。
主な想定被害は以下の通りです:
- 観光客や宿泊客が孤立し、迅速な避難が困難に
- 温泉施設や観光インフラの被害による経済的打撃
- 首都圏からの交通遮断による広域的な混乱
- 火山灰による健康被害や生活環境の悪化
現在の警戒レベルは「レベル2」となっており、気象庁と地元自治体は連携して常時監視と防災対策を進めています。
箱根山の美しい自然と温泉は、多くの人に癒しをもたらしますが、その背後には一瞬で生活や観光が停止してしまう“潜在的危機”が存在していることを忘れてはなりません。
なぜ事前の備えが必要なのか?
噴火は予測困難な災害のひとつ
地震や台風と並び、火山噴火もまた日本に暮らす私たちにとって無視できない自然災害のひとつです。中でも火山災害の厄介な点は、「いつ・どこで・どれだけの規模で起きるか」の予測が非常に難しいということ。最新の観測技術が進化しても、突発的な噴火を完全に防ぐことはできません。
降灰、火砕流、泥流…噴火による被害は多様で広範囲に及びます。
火山の種類や噴火のタイプによって、被害の出方も大きく異なります。例えば火山灰は、数十〜数百キロ先まで風に乗って広がり、交通機関の麻痺、電力設備のショート、農作物への被害などを引き起こします。
さらに、火砕流は秒速数十メートルで山麓を襲い、建物も人命も容赦なくのみ込みます。大雨と重なると火山泥流(ラハール)が発生し、河川を下って住宅地に甚大な被害を与える可能性もあります。
では、私たちに今できる備えとは何か?
- ハザードマップを確認し、自宅や職場がどのようなリスク下にあるかを知ること
- 非常時の避難ルートと避難所を家族で共有すること
- 降灰に備えてマスクやゴーグル、ブルーシートなどを備蓄しておくこと
- 自治体や気象庁が発信する火山情報に日ごろから目を向けておくこと
火山災害は、発生してからでは手遅れになるケースが多くあります。だからこそ、「火山は身近な脅威である」と認識し、平時からの備えこそが最大の防災策なのです。明日噴火しても慌てず動けるように――その一歩を、今から踏み出しましょう。
まとめ:火山列島・日本に住むということ
「いつか起きる」は「いつ起きてもおかしくない」
日本列島に暮らすということは、四季の美しさや自然の豊かさと引き換えに、常に地震や噴火といった自然災害と隣り合わせに生きることでもあります。特に火山は、静かに見える時ほど注意が必要な“潜在的リスク”を抱えた存在です。
「いつか噴火するかもしれない」は、裏を返せば「明日でもおかしくない」ということ。実際、過去の大噴火の多くは、前兆があってもごく短期間で発生しています。
しかし恐れるばかりではなく、正しい知識と備えがあれば、命を守り、被害を最小限に抑えることは可能です。この記事で紹介した10の火山は、特に私たちの暮らしに大きな影響を及ぼす可能性を持つものばかり。今一度、火山の現実に目を向け、「備えること=自分と家族を守ること」だと理解しておくことが大切です。
火山列島・日本に暮らす私たちだからこそ、
“いつか”に備えるその意識が、未来を大きく左右するのです。
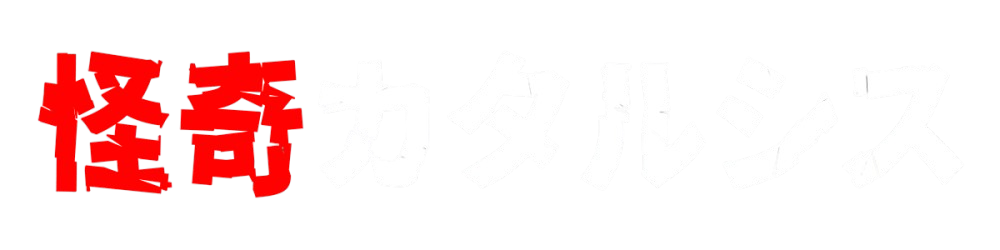

コメント