⏲この記事は約 10 分で読めます。
血族結婚の村(石川県)
石川県の某集落には、いまだに血族結婚の風習が残ってる。
村民の多くは同じ苗字を名乗り、顔は老人から子供までどこか似ており、仕草まで同じ特徴が見られるという。現代日本では血族結婚は倫理的にも法律的にもタブーとされている。
しかしながら日本国憲法においては『本人』『直系血族』『3親等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、おじと姪、おばと甥)』『直系姻族(婚姻関係終了後も継続)』『養親とその直系尊属及び養子とその直系卑属(離縁後も適用)』との婚姻届は受理されないものの、憲法第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」とあるだけで近親者間の性交そのものを禁止しているわけではない。
すなわち、近親者同士であっても事実婚は阻害されないと、ちゃんと定められているのだ。
とはいえ、血が濃くなると障害をもった子供が生まれる確率が高くなったり、犯罪に手を染めやすいといった昔ながらの先入観もあるだろう。
ところが、この村の人々の特徴は、IQや運動能力がズバ抜けて高く、ほとんど病気知らずらしい。
あるマスコミ関係者は言う。
「某村の人々が病気にならないのは、通常では考えられないような強い免疫力を持っているからに違いありません。突発的に、住人の1人が突然変異によって獲得した『特殊能力』が血族結婚によって守られ、代々受け継がれてきたのではないでしょうか」
唯一のマイナス面といえば80歳で胃癌で亡くなる遺伝傾向があるそうだが、そこまで生きられれば御の字だろう。
ではなぜ、今もなお血族結婚の風習が廃れることなく続いているのか。
村を出たという元住人の証言によれば…
数百年前、村は飢饉の打撃を受け、村人のほとんどが餓死する窮地に陥った。この危機的状況を打開すべく、村人らは一計を案じた。村へ嫁ぎに来た女性を『民の花嫁』とするのだ。
一個人に捧げるのではなく、村の男全員に奉仕する役目を負わせたわけだ。
つまり、花嫁は万が一、夫との間に子供ができなくても、村人の誰かの子種を宿すことができれば確率的に子孫繁栄しやすくなる。
一の矢がはずれても、二の矢、三の矢で的を射るべし、ということだ。
婚礼の前日、たった一人実家に残された花嫁は、次から次へと訪れる村の男と交わねばならないという。
新郎はそれを指をくわえて見守るしか術がなかったそうだ。
この『民の花嫁』の風習のおかげで、某村はかつての活気を取り戻したうえ、予期せぬ副産物も得ることができた。
上述した『知能・運動神経が秀でており、なおかつ病気に強い』遺伝子を獲得するに至ったというわけだ。
血族結婚の村とは?
上記では、他の血族結婚の村とは異質の珍しい一例をご紹介しました。
一般的に血族結婚の村とは、特定の血縁関係にある人々が結婚を行う文化的背景を持つ地域のことを指します。日本では、特に長い間その慣習が根付いています。家族の結びつきが強い村においては、血族が結婚することが珍しくなく、その背景には地域の特性や歴史が影響しています。
血族結婚の定義は、特定の血縁者同士が結婚することです。この現象は、地域コミュニティの維持や家族同士の結束を深めるための手段として存在してきました。石川県には、そうした村があり、具体的な事例としては、先祖と同じ名字を持つ者同士の結婚が多く見られます。
現在、このような結婚の傾向はやや変わりつつありますが、依然としてその文化が色濃く残っています。血族結婚は地域の伝統や社会的な要因が絡み合った複雑な現象です。
血族結婚の定義
血族結婚とは、血縁関係にある者同士が結婚することを指します。具体的には、親子、兄弟姉妹、いとこなど、血縁関係が近い者同士の結婚が該当します。法律上、血族結婚には制限があり、特定の親等内の血族同士の結婚は禁じられています。
血族結婚の種類
血族結婚には、以下のような種類があります。
1. 直系血族結婚: 親子や祖父母と孫など、上下の世代間での結婚。
2. 傍系血族結婚: 兄弟姉妹やいとこなど、同じ世代間での結婚。
法律上の制限
日本の民法では、直系血族および三親等内の傍系血族との結婚は禁じられています。例えば、親子や兄弟姉妹、叔父・叔母と甥・姪などが該当します。
血族結婚はなぜ行われるのか?
血族結婚はなぜ行われるのか?それにはいくつかの理由があります。
結論として、血族結婚は特定の文化や地域に根付いた伝統であり、そこには様々な社会的、経済的な要因が影響しています。
理由としては、まず家族同士の結びつきを強化するためがあります。特に田舎の村では、土地や資源を守るために親密な関係が求められることがあります。また、結婚相手が血縁関係にあることで、家族の絆が深まり、世代を超えた共同体が形成されやすいのです。
具体例として、石川県のある村では、古くから親族同士の結婚が行われてきました。地域の文化や習慣に根ざしたこれらの結婚は、村人たちの生活や価値観に深く結びついています。飲食店や商店も、血族結婚で強固な支え合いがなければ成り立たない場合があります。
血族結婚はリスクが高いと思う人もいるかもしれませんが、実際には地域独特の習慣や信念が根底にあります。リスクを承知の上で、地域の伝統を重んじる文化が存在するのです。
血族結婚はその地域の歴史や社会構造が反映されたもので、文化的な背景が重要な要素となっています。
日本の血族結婚の歴史
日本の血族結婚の歴史は、古代から現代に至るまで、社会や文化の変遷とともに変わってきました。ここでは、古代から平安時代、そして現代までの血族結婚の歴史をわかりやすく解説します。
古代の血族結婚
古代日本では、血族結婚は比較的一般的でした。特に、権力を維持するために、貴族や豪族の間で近親婚が行われていました。これにより、財産や地位を外部に流出させないようにしていました。
平安時代の血族結婚
平安時代になると、貴族社会では血族結婚がさらに重要な役割を果たしました。特に、藤原氏などの有力貴族は、天皇家との婚姻関係を通じて権力を強化しました。藤原道長は娘たちを天皇に嫁がせることで、摂政や関白としての地位を確立しました。
平安時代の結婚制度は、初期には「妻問い婚」と呼ばれる形態が主流でした。夫が夜に妻の家を訪ね、朝には自分の家に帰るという形式です。中期になると、夫が妻の家に同居する「婿入婚」に変わり、後期には夫婦が独立して新居を構える「経営所婿取婚」が一般的になりました。
中世から近世の血族結婚
中世以降、武家社会でも血族結婚が行われました。例えば、足利将軍家や徳川家などの支配層では、いとこ婚やまたいとこ婚が推奨されました。これにより、家系の純粋性を保ち、権力を集中させることが目的でした。
近代から現代の血族結婚
近代に入ると、血族結婚は次第に減少しました。明治時代には、近親婚を制限する法律が制定され、現代では法律で禁止されています。しかし、天皇家では、近親婚が行われた例もあります。例えば、昭和天皇と香淳皇后は、いとこ同士の結婚でした。
日本の血族結婚の歴史は、時代とともに変化してきました。古代や平安時代には権力維持のために重要な役割を果たしましたが、近代以降は法律で制限され、現代ではほとんど見られなくなりました。それでも、歴史を通じて血族結婚がどのように社会や文化に影響を与えてきたかを理解することは重要です。
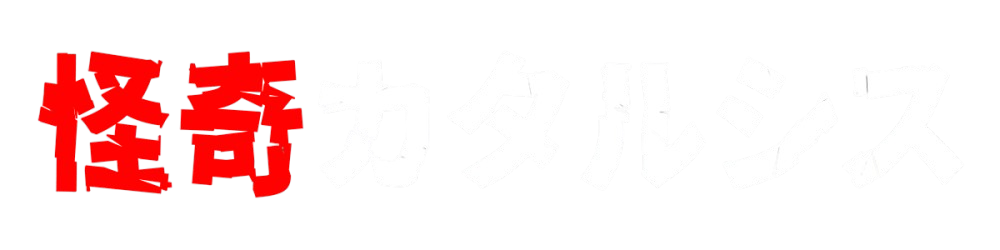
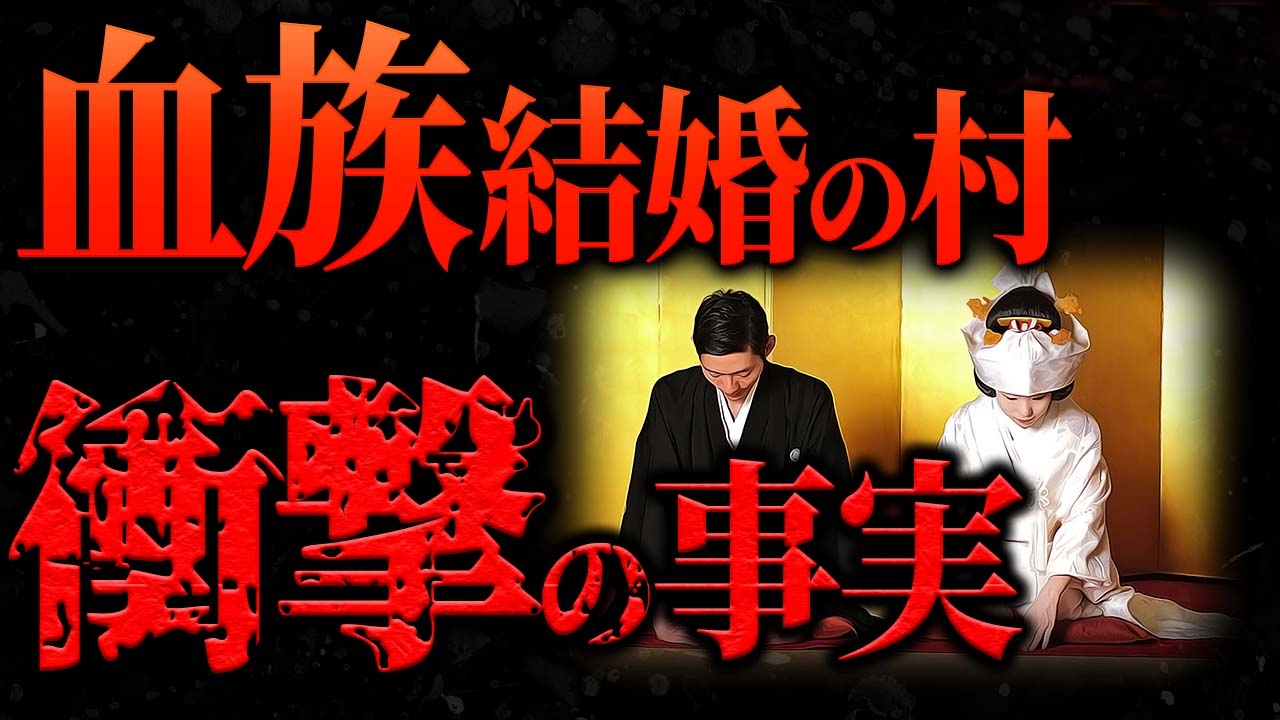
コメント